[st-kaiwa2]「自律神経」で多くの人がつまずく原因って何ですか?[/st-kaiwa2]
[st-kaiwa1 r]「丸暗記だけにたよる」ことです。ズバリつまずく原因は「理解できていないこと」なんです。[/st-kaiwa1]
[st-kaiwa2]暗記と理解どちらも求められるから混乱するんですね?[/st-kaiwa2]
[st-kaiwa1 r]そうなんです。初めは覚えるより理解に重点をおきましょう。[/st-kaiwa1]
- 覚えることが多いこと
- 理解すること
この2つを分けて取り組みましょう。
[st-kaiwa3]こんにちは!
今回の解説をしているBeken(beken77116525)といいます。
現在ドラッグストアで「店長」と「管理薬剤師」を兼任している現役薬剤師です。
現場経験も30年以上で登録販売者に関しては設立から見てきましたのでリアルな話ができると思います。[/st-kaiwa3]
新規に勉強を始める時にほとんどの人は1章からスタートしますよね。
順に読み進めると「突然」医薬品の名前が出てくるのが3章です。
みんなここで軽いパニックに陥ります。
焦ると「丸暗記で乗り切ろう」思考になりやすいので要注意です。
「自律神経」は1つ1つ理解していけば全体像が把握できます。
一度分かってしまえば3章全体の理解がスムーズです。
医薬品名の詰め込みは後からでも大丈夫。
まずは暗記よりも理解を深めましょう。
「自律神経」の他につまずきやすいポイントとして「抗ヒスタミン薬」があります。
優先的に理解すべき内容を別ページにまとめているので参考にして下さいね。
初めに理解したいところをリストアップしておきます。
- 自律神経ってなに?
- 「交感神経」と「副交感神経」
- 神経伝達物質
- 自律神経に使われる用語について
それではゆっくり進めていきましょう!
自律神経ってなに?

まずは神経の種類(神経系)にはどんなものがあるのか見ていきましょう。
早速「クラッときた」あなた!
細かく理解しようとすると混乱するので「神経=電気の線」のイメージして下さい。
「脳みそから電気が電気の線を伝わって手や足が動く」ぐらいに軽い気持ちでいきましょう。
神経が色々出てきますが「自立神経」に今は注目して下さい。
「自律神経」は無意識で心臓や肺などの臓器をコントロールしています。
腕や足は自分で動かせますが心臓は動かせないですよね。
| 神経系 | |||
|---|---|---|---|
| 中枢神経 | 末梢神経 | ||
| 脳 | 脊椎 | 体制神経 | 自律神経 |
神経系
神経系とは体内の情報伝達を行う組織です。
- 中枢神経:脳と脊椎からなる、体の働きを制御する神経
- 末梢神経:中枢神経によって制御される神経
体制神経系
体制神経は知覚神経と運動神経に分類されます。
- 知覚神経:外部からの情報を集める神経。
- 運動神経:脳の指令を骨格筋に伝え随意運動を起こさせる神経。
末梢神経系
末梢神経はは脳・脊椎からからだに伸びる神経です。
体制神経系と自立神経系に分類されます。
自律神経系
自律神経は交感神経と副交感神経に分類され、からだや身体機能の維持を無意識に行います。
- 交感神経:からだが緊張状態に対応できるように働く神経。
- 副交感神経:からだが安静状態になるように働く神経。
「交感神経」と「副交感神経」



自律神経の位置付けを理解するたに神経系を分類しました。
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」から成り立ちます。
自律神経は例えば心臓のように無意識に働く神経なのでイメージしにくいですよね。
さらに話をややこしくするのが自律神経の「二重支配」です。
自律神経は「交感神経」と「交感神経」2つのバランスで考えなければなりません。
自律神経の「二重支配」
自律神経でつまずくポイントは自律神経の二重支配です。
人のからだ(自律神経)は交感神経と副交感神経のバランスによって支配されています。
まずは下の評を見てください。
| 効果器 | 交感神経優位 | 副交感神経優位 |
|---|---|---|
| 目 | 瞳孔拡大 | 瞳孔収縮 |
| 心臓 | 心拍数増加 | 心拍数低下 |
| 抹消結館 | 収縮(血圧上昇) | 拡張(血圧低下) |
- 交感神経優位:緊張・興奮状態
- 副交感神経優位:リラックス状態
※例外はありますが登録販売者の試験範囲ではこの認識で理解しましょう。
交感神経が優位にあるなら緊張・興奮状態です。
目を例にすると交感神経が優位なときは瞳孔が開きます。
副交感神経が優位のならリラックス状態です。
心臓を例にすると、副交感神経が優位なときは脈拍が下がります。
自律神経の二重支配は色々な例えをされますがリレーに例えるとわかりやすくなります。
「交感神経」と「副交感神経」の優位な方が勝ち臓器に現れる状態が変化するからです。
このバランスは無意識に行われていますが、意図的にコントロールすることで作用する「医薬品」。
副作用として影響がでてしまう「医薬品」があるため十分理解することが大切です。
神経伝達物質
自律神経をリレーに例えたのにはもう1つ理由があります。
リレーに使うバトンってありますよね?
バトンが非常に大切です。
神経を電気の線に喩えましたが脳から臓器までが1本の線で直接繋がってはいません。
「交感神経」や「副交感神経」は途中でバトンタッチをして情報を伝えています。
神経と神経の間で情報を伝達するものなので「神経伝達物質」という名前です。
リレーで各チームのバトンの色が違うように「交感神経」と「副交感神経」によって違います。
- 「交感神経」チームのバトン(神経伝達物質):「ノルアドレナリン」
- 「副交感神経」チームのバトン(神経伝達物質):「アセチルコリン」
自律神経に使われる用語
リレーの醍醐味はやはりバトンタッチですよね?
選手の速さが拮抗していても勝負を左右します。
自律神経に登場する医薬品はバトンタッチのところに着目しています。
勝たせたいチームの手助けをしたり相手チームの邪魔をして「臓器の動きをコントロール」する発想です。
「アドレナリン」作動成分
交感神経チームのバトンタッチを手助けをします。
交感神経を優位にする働きを持つ成分です。
「抗アドレナリン」作動成分
交感神経チームの邪魔をします。
交感神経の働きを邪魔することで、副交感神経を優位にします。
「コリン」作動成分
副交感神経チームの手助けをします。
副交感神経を優位にする働きのある成分です。
「抗コリン」作動成分
副交感神経のバトンタッチを妨げる働きの成分です。
副交感神経の働きを低下させることで相対的に交感神経を優位にする働きです。
実際の使用例
〈使用例〉
抗コリン成分の医薬品を使用する際は、心臓病または緑内障の診断を受けたものは症状が悪化するため使用前に相談すること。
〈解説〉
抗コリン成分は副交感神経の働きを妨げる働きです。
結果として交感神経が優位となります。
上の表で心臓の欄で交感神経が優位な場合を確認すると心拍数は増加することが分かります。
よって、抗コリン成分を使用する際は心臓病のある方への使用は慎重に行う必用があります。
まとめ
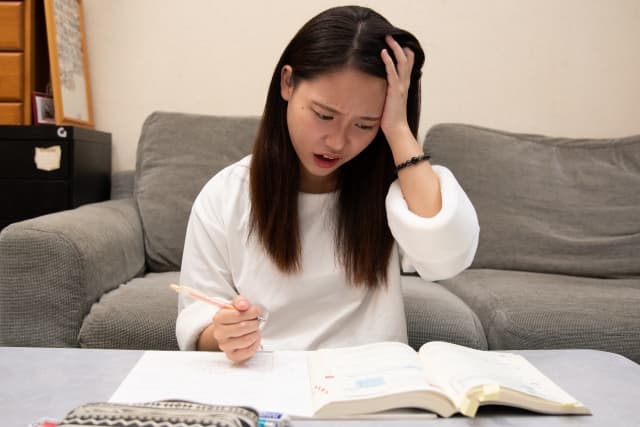
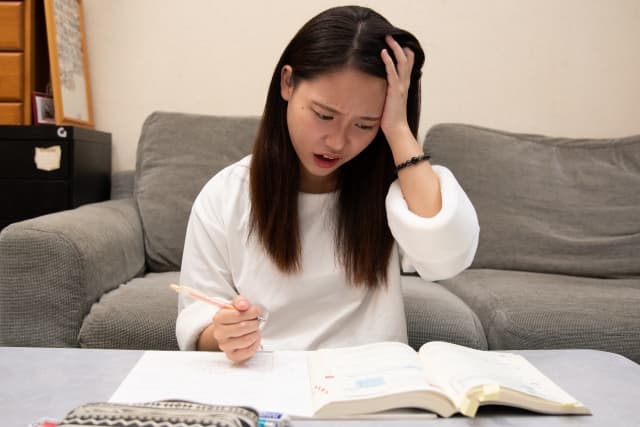
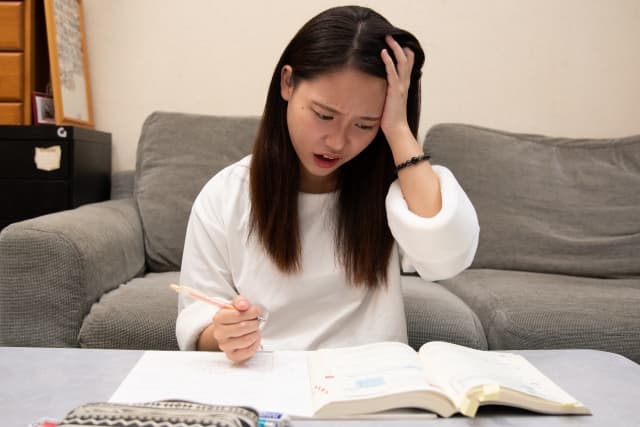
一度読んだだけだとかなり混乱しませんか?
「登録販売者」のテキストで勉強を始めるとこの辺の説明が無いまま進んでいきます。
理解でできていないとなんで???となりやすいところです。
「登録販売者試験」で医薬品の理解を深めるためには必須の知識となります。
繰り返し読んで早い段階で理解しておきましょう!
さらに自律神経の二重支配や神経伝達物質について理解できていれば良い点があります。
抗コリン成分を使用すると、(相対的に交感神経が優位となり結果として)心拍数が増加する。
こんな表現をする場合に間の括弧の部分は省略できます。
「急がば回れ」面倒なところほど初めに片づけて後で楽しましょう。
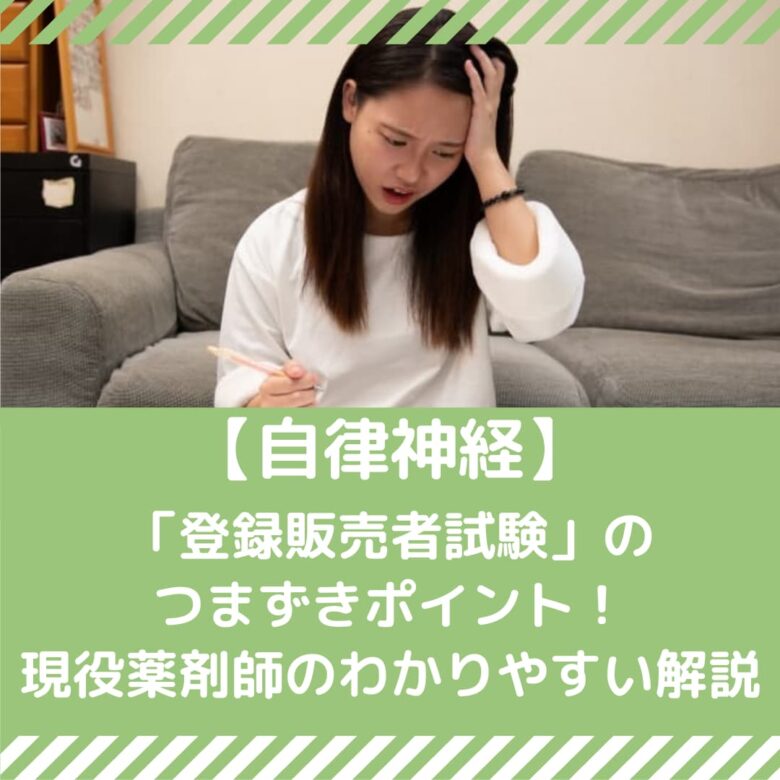








コメント